
3. 河川生態系を工学から理解する
 |
3. 河川生態系を工学から理解する |
|---|
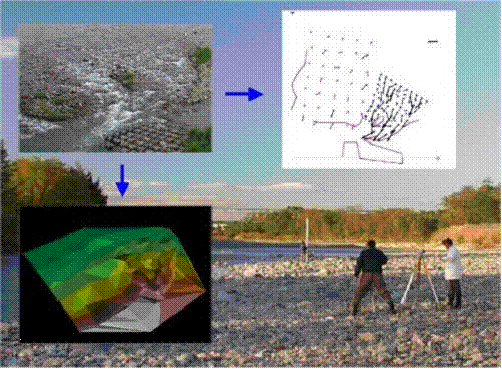
近年、多くの河川で近自然工法が取り入れられ、多自然川づくりと呼ばれる環境に配慮した川づくりがなされるようになってきました。 しかし、治水や利水の目標に比べて、多くの生物が棲む川を復元しようという目標はまだまだ達成できていないように思います。 この原因としては、その目標像に加え、具体的な対策が曖昧であることが挙げられます。 特に、河川に生息する様々な生物に配慮しつつ河川の自然再生を薦める上では、生態学の知見と河川工学の知見の融合が必要不可欠です。 なぜなら、生物のすみ場は洪水など自然の力で形成されているために、流れ場や地形、あるいはそれらの相互作用を工学的視点から捉えなければ、その理解を深めることはできないからです。 そこで、工学的な視点から河川流域の生態系あるいは河川流域の景観を捉え、その改善策を考えようというのが、我々の目指す『生態基盤工学』のアプローチです。
すなわち、我々の研究対象は、「流域の自然特性に様々な人為的影響が加わることで、その場所の物理基盤が形成され、その物理基盤に応じた生物相が定着し、結果として流域・河川景観が形成される」という一連のメカニズムです。 このメカニズムを明らかにすることで、何を保全し、何を再生し、何をどの程度調整すれば、川の個性、あるいは、その流域全体の個性を再生することができるのかを把握し、治水や利水の要求を満たしつつも、多くの生物が生息し魅力的な河川流域を再生する手法を見いだせるという理念の元、研究を進めています。
『川を見る』と一言で言っても着目する要素は様々です。 そもそも、そこにはどの様な河川が流れているべきかを考える際には、対象がどのような流域地形なのか、そこにはどの様な地質的特徴があり、どのような土地利用がなされているか、といったことから考えなければなりません。 一方で、石の上の藻、河原の草、水中を泳ぐ魚が棲める環境を考えるときには、石の間に砂がどのように詰まっており、その周りにどの様な流れの構造が見られるのかを考えなければなりません。 このように、流域全体の特徴を捉えるスケール、山地、丘陵地、台地、扇状地、平野ごとに特徴を捉えるスケール、堤防の上に立って川全体の風景を眺めるスケール、河原、瀬、淵の構造を把握するスケール、川の礫一つ一つの積み重なり方を調べるスケール、などが存在し、上のスケールは下のスケールの状態を支配し、下のスケールの状態が上のスケールの景観を構成していますが、河川環境はこれらすべてのスケールから解析する必要があります。 我々は、各メンバーが興味を持った、河川景観・生態系等の対象を、階層的に河川環境を解析・評価しています。
“河原”、“瀬”、“淵”等の場は、河川生態系を支える重要な基盤です。 しかし、こうして古くから重要視されてきた瀬と淵も、「どういった瀬、淵がよいのか?」「どうすればそのような瀬、淵ができるのか?」に関しては十分議論されておらず、自然再生事業も手探りの状態が続いています。 我々は、自然の力と人為的インパクトの相互作用によって、どのような河床形態が生まれるのか、そしてそれが生物にとってどのような役割を果たしているのか、の双方について河川工学的な視点からの解析を行っています。 また、こうした研究を進める上では、デスクワークや室内実験も当然必要ではありますが、何より現地に何度も足を運び、様々な調査を進めることが重要です。 何度も足を運ぶことで初めて見えてくるものは非常に多いです。
我々は、現地における環境調査に重点を置き、測量や水理量計測といった観測を様々な観測フィールドで行いつつ、「川の個性とは何か?」という問に対して、帰納的に解を導こうとしています。 とはいえ、川の特性、とくに地理学や生態学に関する解析等は我々だけでは不十分であります。 そこで、魚類、底生昆虫、藻類、植物、地理、地質など、各分野の研究者の皆様との合同研究・意見交換を行うことで、新たなアプローチを探っています。 また、同じ河川工学の研究室でもその研究対象やアプローチには大学ごとに個性があります。 そこで、他大学の河川工学の研究室とも合同ゼミを定期的に行い、お互いの手法を見直す機会を設けています。 この様な様々な人達との合同研究・ゼミを通して、様々な視点から河川・流域を捉えることを目指しています。